
くらしのヒント箱
外壁に防犯カメラを設置したいと考えたとき、「壁に穴開けたくない」という理由から、両面テープを使ったDIYを検討する人は少なくありません。
特に外壁に防犯カメラを両面テープで取り付けたい方の多くは、ビス止めによる固定ではなく、できるだけ手軽で目立たず、かつ壁を傷つけない方法を探しているはずです。
しかし、両面テープによる設置には「落ちるのでは?」という不安も付きまといます。屋外は気温や湿度、風雨の影響を受けやすいため、正しい選び方や施工方法を知らずに使ってしまうと、カメラが落下してしまうリスクもあるのです。
この記事では、両面テープで外壁に防犯カメラを設置する際の注意点や、落下防止の工夫、またビス止めとの違いや他の固定方法との比較などを詳しく解説します。実践的な情報をまとめていますので、ぜひ参考にしてください。
この記事で分かること
- 両面テープで防犯カメラを外壁に設置する方法と注意点
- 両面テープが落ちる原因と対策
- ビス止めや他の固定方法との違い
- 壁に穴を開けずに設置するDIYの工夫
本ページはプロモーションが含まれています
外壁に防犯カメラを両面テープで設置する際の注意点

くらしのヒント箱
- 両面テープでは落ちる?原因は
- 両面テープを屋外使用する際の対策
- ゴリラテープは効果的?
- 外壁に防犯カメラを固定するときに気をつける点
- 外壁に穴あけで防犯カメラを設置するリスク
- 固定方法の種類と比較
- 壁に穴開けたくない:DIYでの工夫
- 壁に穴開けたくない:屋外設置の方法
両面テープでは落ちる?原因は
防犯カメラを両面テープで固定したものの、しばらくして落下してしまうというケースは少なくありません。
これは両面テープの選定や貼り方、外部環境など、いくつかの要因が重なって発生する問題です。落下を防ぐためには、原因を正しく理解しておくことが重要です。
まず、最も多い原因は「両面テープの接着力不足」です。市販の一般的な両面テープは、軽量のポスターやプラスチック小物向けに作られていることが多く、重量のある防犯カメラには適していません。
特に屋外に設置するタイプのカメラは300gを超えるものもあり、接着面が小さい場合には支えきれずに落下するリスクが高まります。
次に、外壁の素材や状態も大きな影響を与えます。たとえば、ザラザラとしたモルタルや凸凹の多い外壁材は、テープが十分に密着せず、時間の経過とともに剥がれやすくなります。
また、ホコリや湿気、油分などが付着していると、テープ本来の接着性能が発揮されません。
加えて、温度変化や紫外線の影響も見逃せません。日中に温められた外壁が夜間に急激に冷えると、テープが伸縮を繰り返し、接着力が低下します。特に真夏や真冬はその影響が大きく、数週間で落下することもあります。
このような落下リスクを回避するには、「屋外対応」「高耐荷重」「粗面対応」といった特徴を持つ両面テープを選ぶことが基本です。
そして、取り付け前には外壁の清掃と脱脂をしっかり行い、テープの全面がしっかり密着するように圧着することも重要なポイントです。
つまり、両面テープの落下原因は、テープの性能だけでなく、設置環境と使い方に大きく左右されるのです。これを理解したうえで適切に施工すれば、落下トラブルを大幅に減らすことができます。
両面テープを屋外使用する際の対策
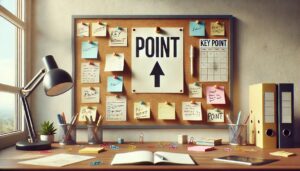
くらしのヒント箱
屋外に防犯カメラを設置する際、両面テープだけで固定するのは不安という方は多いでしょう。
確かに、屋外は天候や温度変化、風圧などの影響を受けやすく、室内と比べて設置環境が厳しくなります。
ただし、いくつかのポイントを押さえることで、両面テープでも比較的安定した設置が可能です。
まず、使用する両面テープは「屋外対応」と明記された製品を選びましょう。中でも「耐水性」「耐熱性」「耐寒性」があるかは重要なチェックポイントです。
また、耐荷重についても確認し、設置するカメラの重さに見合った性能があるかを把握しておく必要があります。
屋外使用での最大のポイントは「接着面の処理」です。以下のような準備をすることで、接着力が大きく向上します。
-
設置面の汚れをアルコールなどでしっかり拭き取る
-
湿気が多い日や雨天を避けて施工する
-
貼り付けた後、数時間は荷重をかけずに静置する
これらの手順を怠ると、どれだけ高性能な両面テープを使用しても、粘着力を発揮できません。
また、両面テープのみでの設置が不安な場合は、補助的に結束バンドやステンレスワイヤーを使って支える方法もあります。例えば、雨樋や柱に軽く巻き付けることで、落下防止の役割を果たします。
さらに、カメラ本体の重量を軽いタイプに変更することも有効です。最近では、電池式で小型軽量のカメラも多く販売されており、両面テープでの設置に適しています。
このように、両面テープを屋外で使用する際には「適切な製品選び」と「事前準備」「補助策」の3点を意識することが、設置成功のカギとなります。
ゴリラテープは効果的?

くらしのヒント箱
防犯カメラの設置において「ゴリラテープ」を使うという選択肢は、一部のユーザーの間で注目されています。
市販の中でも特に強力な粘着力を誇る製品であり、ホームセンターやオンラインショップでも高評価を得ているからです。
しかし、実際に防犯カメラ用途として「効果的かどうか」を判断するには、いくつかの視点から検討する必要があります。
まず、ゴリラテープには数種類のタイプがありますが、一般的に「ゴリラ両面テープ」は、屋外でも使用可能でありながら高い粘着力を持っている点が特徴です。
耐水性や耐熱性も備えているため、外壁に取り付ける場合でも安定した接着力が期待できます。
ただし、どのタイプのゴリラテープも万能ではありません。特に以下のようなケースでは注意が必要です。
-
外壁が凸凹していて、テープ全体が密着しにくい場合
-
高温になる金属外壁や、寒冷地で凍結する場所
-
重量が500gを超える大型カメラを取り付ける場合
これらの状況では、いくらゴリラテープといえども、経年劣化や外的要因によって剥がれやすくなることがあります。
一方で、以下のようなメリットもあります。
-
ビスを使わずに設置できるため、壁に穴を開けたくない人に適している
-
短時間で設置が完了する
-
必要に応じて取り外しやすい(粘着剤の除去はやや手間)
したがって、ゴリラテープは「軽量の防犯カメラを、比較的平滑な屋外の壁に取り付ける」場合には非常に効果的です。
ただし、テープだけに頼るのではなく、定期的に接着状況を確認することや、落下防止用の補助策を併用することが望まれます。
このように、ゴリラテープは条件次第で優れた選択肢になり得ますが、使用環境や設置方法をしっかり見極めることが大切です。
外壁に防犯カメラを固定するときに気をつける点

くらしのヒント箱
ここでは、外壁に防犯カメラを固定するときの注意点を整理します。購入前の確認から施工時、設置後のチェックまでを順に見ていけば、やり直しやトラブルを避けやすくなります。
まず、事前確認として以下を押さえます。
-
カメラの重量と取付方式(ネジ穴の規格、台座のサイズ、付属ブラケットの有無)
-
電源方式(AC、PoE、電池)と配線経路。屋外延長が必要なら耐候ケーブルを前提に計画する
-
設置高さと画角。通行人の顔が適切に写る高さか、夜間に逆光にならないか
-
外壁材の種類(サイディング、モルタル、タイル、ALC、金属板)と下地位置。固定具の適合が変わります
-
管理規約や賃貸契約の可否、近隣のプライバシー配慮(撮影範囲の配慮、マスキング機能の活用)
施工時のポイントは、固定強度と防水性の両立です。ビス止めなら下地を狙い、適切なアンカーとステンレス製ビスを選びます。
穴周りは防水シーリングやブチル系防水テープで一次・二次シールを意識すると、浸水リスクを下げられます。
両面テープでの固定は、外壁の脱脂・乾燥・圧着時間の確保が不可欠で、貼付直後に荷重をかけない配慮が求められます。
環境要因への対策も欠かせません。直射日光や強風、塩害、結露は固定部の劣化を早めます。
軒下や風の抜けにくい面を選ぶ、金属外壁では異種金属接触腐食を避けるためスペーサーを挟む、といった配慮が有効です。配線は雨垂れ線の下に出さず、U字ループ(ドリップループ)で水の侵入を防ぎます。
安全面では高所作業の基本を守ります。脚立は水平に設置し、二人以上で作業すると安心です。最後に、定期点検のしやすさも重要です。
清掃やバッテリー交換に届く位置か、固定部やシールの点検が可能かをイメージしておくと、維持管理が楽になります。
一方で、見た目の配慮も忘れないほうが良いでしょう。外壁色に近いブラケットや配線モールを選べば、外観への影響を抑えられます。
こう考えると、外壁への負担、耐候、メンテ性、景観の四点を軸に固定方法を選ぶ姿勢が大切だといえます。
外壁に穴あけで防犯カメラを設置するリスク

くらしのヒント箱
外壁に穴をあけて防犯カメラを固定する方法は、強度と安定性に優れています。いずれにしても、穴あけには明確なリスクが伴うため、把握した上で適切に対処する必要があります。
代表的なリスクと起こり得る事象、対策例を以下にまとめます。
| リスクの種類 | 起こり得る事象 | 対策の例 |
|---|---|---|
| 雨水浸入 | 断熱材や下地木材が濡れて腐朽、カビ発生 | 穴縁の面取り、下穴清掃、プライマー塗布、ブチル系防水テープ+変成シリコンで一次・二次シール |
| 仕上げ損傷 | タイルやモルタルの欠け、クラック | 適合ビット使用、振動ドリルの負荷を最小化、目地狙いの検討、養生テープで表面保護 |
| 構造・設備干渉 | 背面の胴縁、電線・配管を誤って傷つける | 下地探知、配線経路の事前把握、浅い下穴から段階拡径、貫通深さの制御 |
| 腐食・緩み | ビスやアンカーの錆び、長期での固定力低下 | ステンレス/溶融亜鉛めっき品の選定、異種金属接触を避ける、トルク管理 |
| 規約・保証 | 管理規約違反、外壁保証の消失 | 書面で許可を取得、原状回復方法を明確化 |
| 景観・資産価値 | 穴跡やシーリング痕が残る | 目立たない位置や色合わせ、撤去時の補修プランを事前に用意 |
もし穴あけが避けられない場合は、まず下地と配線の位置を把握します。ここで、探知器や既存コンセントの位置関係から配線ルートを推定すると、事故の可能性を減らせます。
次に、適合するアンカー(窯業系サイディング用、ALC用、コンクリート用など)を選び、推奨下穴径と締付トルクを守ります。
仕上げは防水最優先で、シール材の打ち増しや定期点検の計画まで含めて施工すると安心です。
逆に言えば、賃貸や分譲マンションの共用部では原則として穴あけは難しく、原状回復義務やトラブルを招きやすくなります。
こうした環境では非破壊の固定手段を検討し、管理者と事前に相談しておく姿勢が望ましいです。
固定方法の種類と比較

くらしのヒント箱
固定方法は一つではありません。外壁の材質、許可の可否、期待する耐久性、撤去のしやすさを基準に選ぶと迷いにくくなります。主な方式を比較すると次の通りです。
| 固定方法 | 強度の目安 | 外壁への影響 | 屋外適性 | 撤去の容易さ | 向く条件・注意点 |
|---|---|---|---|---|---|
| 両面テープ(屋外用) | 中(軽量機向け) | 低 | 中 | 高 | 平滑面で有利。粗面は密着不足に注意。貼付前の脱脂・圧着・養生が鍵 |
| 両面テープ+補助バンド | 中〜やや高 | 低 | 中 | 中 | 雨樋や柱に結束で落下防止。長期はバンド劣化を点検 |
| クランプ・バンド固定(柱・手すり) | 中〜高 | 低 | 高 | 中 | 穴不要。丸柱や格子で有効。締め過ぎによる歪みに注意 |
| マグネットマウント(金属外壁) | 中 | 低 | 中 | 高 | 強磁力品を選定。高温で磁力低下の可能性、落下対策を併用 |
| ビス止め(下地固定) | 高 | 中〜高 | 高 | 低 | 恒久設置向け。防水処理と適合アンカーが前提 |
| ケミカルアンカー・コンクリートアンカー | 非常に高 | 高 | 高 | 低 | 重量機や高所に有効。撤去補修は手間がかかる |
| 吊り金具・軒天ブラケット | 高 | 中 | 高 | 中 | 軒下で雨避け可。下地確認と防火仕様の適合確認 |
| 自立スタンド(三脚・ベース) | 低〜中 | なし | 低〜中 | 高 | 屋内や仮設向け。転倒防止の加重が必要 |
| 吸盤マウント | 低 | 低 | 低 | 高 | 恒久用途には不向き。短期の仮設・室内ガラス向け |
他にも、コーナーブラケットで建物の角に取り付ける方法や、配線モール一体型のベースを用いる方法があります。
前述の通り、屋外で両面テープを使う場合は下地の状態と養生時間が成果を左右します。ビス止めは長期安定が得られる一方、穴あけリスクと原状回復の手間を伴います。
選び方の目安を簡潔にまとめます。
-
賃貸や原状回復必須なら、クランプやマグネット、両面テープ+落下防止の組み合わせが無難
-
恒久的に強固な固定が必要なら、下地を狙ったビス止めや適合アンカーを検討
-
海沿い・強風地域は、金具と防錆材を重視し、念のため二次的な落下防止を追加
-
小型・軽量の電池式カメラは、非破壊の固定手段と相性が良い
もし迷ったら、想定耐用年数と撤去時の工数、外壁への影響を点数化して比較すると判断しやすくなります。こうして要件を見える化すれば、過不足のない固定方法にたどり着けます。
壁に穴開けたくない:DIYでの工夫
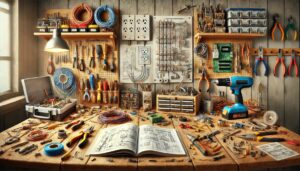
くらしのヒント箱
防犯カメラを設置したいけれど、壁に穴を開けたくないという方は少なくありません。
特にDIYで設置する場合、工具の扱いや原状回復の不安から、できるだけ非破壊で設置できる方法を探す傾向にあります。
ここでは、壁にダメージを与えずにカメラを取り付ける工夫について紹介します。
まず最も手軽な方法は、「強力両面テープ」の活用です。現在では、屋外対応・高耐荷重タイプの両面テープが各社から販売されており、200~500g程度のカメラであれば十分に固定できます。ただし、使用時には以下の点に注意が必要です。
-
壁面は事前に中性洗剤やアルコールで汚れを除去し、乾燥させてから貼り付ける
-
凸凹のある壁面やザラザラした素材には不向き
-
両面テープ貼り付け後は24時間以上放置し、完全に密着させる
このようにすれば、落下リスクを最小限に抑えることができます。
もう一つの方法は「クランプ固定」や「結束バンド」です。たとえば、屋外に設置されたポールやフェンス、雨樋などに市販のクランプ金具や結束バンドでカメラの台座を固定することが可能です。
この方法なら、壁に接触せずに設置ができ、撤去も簡単に行えます。ポイントは以下のとおりです。
-
素材が金属の場合はバンドで締めすぎないこと(外装の変形を防ぐ)
-
雨どいなど樹脂製素材の場合は、重さのかかる位置に注意
-
強風に備え、念のため落下防止ワイヤーを併用する
さらに応用的な方法として「自立スタンド型カメラ」を選ぶという選択肢もあります。これは台座が付属しており、地面や棚、ベランダの床などに直接置いて使用できるタイプです。
特に電池式でWi-Fi接続可能なモデルは、電源工事や配線も不要なため、DIY初心者にも扱いやすい仕様となっています。
他にも、マグネット式マウントを使って鉄製の門柱や玄関ドアに取り付ける方法もあります。ただし、磁力の強度や金属面の塗装状態によっては、安定性に欠けることもあるため、定期的な点検を心がけましょう。
このように、DIYでも壁に穴を開けずに防犯カメラを設置する方法はいくつも存在します。工夫次第で十分に安定した設置が可能になるため、住環境や対象となる場所に合わせて最適な手段を選びたいところです。
壁に穴開けたくない:屋外設置の方法
屋外に防犯カメラを設置したいけれど、外壁に穴を開けたくないというニーズは非常に多くあります。
特に持ち家でも外観を損ないたくない場合や、賃貸住宅などで原状回復義務がある場合は、非破壊での設置方法を選ぶ必要があります。
ここでは屋外設置に適した“穴を開けない”固定方法を紹介します。
まず候補として挙げられるのが「屋外対応の強力両面テープ」です。これは簡単かつ安価に設置できる方法で、以下のような場面に適しています。
-
軽量カメラ(おおむね500g以下)の取り付け
-
外壁が比較的平滑な場合(サイディング、金属パネルなど)
-
直射日光や雨が直接当たりにくい軒下などの環境
この方法を成功させるためには、テープの選定が極めて重要です。「耐候性」「防水性」「粗面対応」と明記されている商品を選び、取り付け前に壁面の脱脂と乾燥を十分に行いましょう。
取り付け後はすぐにカメラを取り付けず、数時間以上待ってから設置すると接着力が安定します。
次におすすめなのが「クランプ式ブラケット」の使用です。これは手すり、雨樋、ベランダの柵などに金具を挟み込む形で固定する方法で、壁に接触しないため非常に便利です。
注意点としては、対象となる支柱の径や形状に合った金具を選ぶこと、過度な締め付けによる破損を避けることが挙げられます。
また、「マグネットマウント」を使う方法も有効です。鉄製の柱や門扉、配電ボックスなどに磁石で固定するため、工具不要で着脱が可能です。
ただし、磁力だけに頼ると風で落下する可能性があるため、落下防止の補助バンドや滑り止めシートを併用すると安心です。
さらに、「三脚スタンド」や「プランター設置台」などを活用することで、地面からの設置も可能です。これらは玄関前や庭、ベランダで活用されるケースが多く、以下のような利点があります。
-
カメラの高さや角度を自由に調整しやすい
-
移動可能なので、用途に応じて撮影範囲を変えられる
-
地面や床に重りを置いて安定させれば、強風にも対応できる
どの方法にも共通していえるのは、「落下リスクへの備え」が重要という点です。屋外では天候の変化や風の影響を受けやすいため、固定強度を過信せず、補助的な固定手段や定期点検を取り入れることが大切です。
このように、壁に穴を開けずに屋外へ防犯カメラを設置する方法は多岐にわたります。設置環境やカメラの重量、電源方式に応じて最適な方法を選べば、壁を傷つけることなく安全に運用することが可能です。
外壁に防犯カメラを両面テープで固定する方法まとめ

くらしのヒント箱
- 壁に穴開けたくない:室内設置の方法
- 外壁にビス止めする方法との違い
- 両面テープの選び方
- 両面テープの耐久性はどれくらい?
- 両面テープと他の粘着素材の比較
- 防犯カメラの落下を防ぐための工夫
- 両面テープで固定後のメンテナンス方法
壁に穴開けたくない:室内設置の方法
室内に防犯カメラを設置する場合、壁に穴を開けずに取り付けたいというニーズは非常に多くあります。
特に賃貸住宅や分譲マンションでは、原状回復の必要があるため、壁への加工を避けたいと考えるのは自然なことです。ここでは、室内で壁に穴を開けずに設置できる具体的な方法をいくつか紹介します。
最も簡単なのは「置き型タイプの防犯カメラ」を選ぶ方法です。これは、三脚スタンド付きや卓上設置が可能なモデルで、テレビ台や本棚、冷蔵庫の上などにそのまま置くだけで使用できます。
電源とWi-Fiが届く範囲であれば、配線もシンプルに済みます。次のような条件に向いています。
-
電池式またはUSB電源で動作する小型カメラ
-
撮影対象が玄関や窓など、限られた範囲の場合
-
レンズの向きを自由に調整したいとき
もう一つの方法が「粘着シートや両面テープで固定する壁掛け設置」です。軽量なカメラであれば、壁紙を傷めにくい粘着ゲルや再剥離タイプの両面テープで十分に固定できます。ただし、以下の点には注意が必要です。
-
使用前に壁面のホコリや油分をきちんと除去する
-
一度貼ったら数時間はそのまま静置して粘着力を高める
-
高温・多湿の場所では剥がれやすいため設置場所を選ぶ
加えて、「突っ張りポール」や「収納棚の側面」などを利用する方法もおすすめです。突っ張りポールに小さな棚板を取り付けてカメラを載せたり、収納棚の側面にマグネット式のマウントを使ったりすることで、壁に加工をせずに高さを出すことができます。
室内での設置は、外部からの侵入を監視する「玄関」「窓周辺」「ベランダ出入り口」などを中心に考えるとよいでしょう。
また、小型カメラであっても夜間対応や動体検知、通知機能がある機種を選ぶことで、より効果的な防犯が可能になります。
このように、室内でも壁を傷つけずに防犯カメラを設置する方法は多彩です。状況に応じて設置場所や固定手段を工夫することで、安心感と原状維持の両立が実現できます。
外壁にビス止めする方法との違い

くらしのヒント箱
防犯カメラの設置方法にはさまざまな種類がありますが、その中でも「外壁へのビス止め」と、ビスを使わない方法との違いは非常に大きいといえます。
ここでは、ビス止めと非破壊型(テープ固定やバンド固定など)の違いを明確に比較しながら、それぞれの特徴を解説します。
まず、ビス止めの最大の特徴は「強力な固定力と耐久性」です。壁の下地に直接ビスを打ち込むため、長期間にわたって安定した固定が可能です。
特に重量のあるカメラや、強風・振動の影響を受ける場所には非常に向いています。ただし、以下のようなデメリットがあります。
-
壁に穴が空くため、原状回復が難しい
-
外壁の種類によっては施工が難しく、下地探しや適切なアンカーが必要
-
防水処理をきちんと行わなければ、雨水が侵入する恐れがある
一方で、ビスを使わない方法(両面テープやクランプ・マグネットなど)は、施工の手軽さが魅力です。以下のような点が特徴です。
-
壁に傷を付けないため、賃貸や新築でも安心
-
工具が不要で、DIY初心者にも取り組みやすい
-
設置場所の変更や取り外しが簡単
ただし、非破壊型の固定方法は、ビス止めに比べると強度面ではやや劣ります。特に夏場の高温や冬の寒さ、雨風の影響を受けやすい場所では、テープの粘着力が低下することがあり、定期的な点検が欠かせません。
また、設置対象が凸凹のある外壁だと密着が不十分になりがちです。
このように、ビス止めと非ビス固定の選択は、設置環境・耐久性・メンテナンス性・原状回復の必要性といった複数の要素をもとに決めるべきです。
たとえば、屋根のある玄関まわりなどではテープやクランプでも十分に機能しますが、風が強く当たる高所ではビス止めのほうが安全性に優れています。
状況に応じて柔軟に使い分けることが、失敗のない設置につながります。
両面テープの選び方

くらしのヒント箱
防犯カメラを両面テープで外壁に設置する場合、最も重要なのが「適切なテープ選び」です。市販されている両面テープにはさまざまな種類があり、見た目が似ていても性能には大きな違いがあります。
間違ったテープを使うと、カメラが数日で落下してしまう恐れがあるため、慎重に選びたいところです。
まずチェックすべきは「耐荷重性能」です。カメラ本体の重さに対して十分な強度があるかを必ず確認しましょう。一般的な目安としては、カメラが300gの場合、耐荷重は1kg以上のテープを選ぶと余裕があり安心です。
次に重要なのが「屋外対応かどうか」です。屋外設置の場合、雨・紫外線・温度変化に晒されるため、以下のような性能が求められます。
-
防水性(テープが水分を吸って剥がれない)
-
耐熱・耐寒性(真夏や冬の温度変化でも粘着力を維持)
-
UV耐性(紫外線で劣化しない)
これらの性能が明記されている商品を選ぶことが、落下リスクを避ける第一歩になります。
また、取り付ける外壁の材質にも注意が必要です。以下のような違いがあります。
| 外壁素材 | 適したテープの特徴 | 注意点 |
|---|---|---|
| サイディング(平滑) | 粘着タイプ全般に対応しやすい | 脱脂と乾燥をしっかり行うこと |
| モルタル・タイル(凹凸あり) | 粘着剤が厚めの粗面対応型 | 凸凹にしっかり圧着しないと剥がれやすい |
| 金属パネル | 熱で変形しにくい耐熱型 | 真夏の高温に注意 |
さらに、施工前の準備も成功のカギです。壁面に油分やホコリがあると粘着力が発揮されないため、アルコールなどでしっかり清掃し、完全に乾いた状態で貼り付ける必要があります。
テープを貼った直後にカメラを取り付けず、数時間は静置してから設置することで、より強力に接着できます。
このように、両面テープを選ぶときは「重量・屋外性能・素材の適合性・下処理」の4つを意識すると、落下トラブルを防ぐことができます。
単純に「強力そうだから」ではなく、使用環境に合った製品を選ぶことが何より大切です。
両面テープの耐久性はどれくらい?

くらしのヒント箱
防犯カメラを設置する際、両面テープを使う方法は手軽さと壁を傷つけない点で人気があります。しかし、気になるのはその「耐久性」です。
カメラは屋外で数年にわたって使用することが多いため、途中でテープが剥がれて落下するようなことがないか、事前に確認しておくことが大切です。
両面テープの耐久性は、主に以下の4つの要素に左右されます。
-
テープの材質と構造
-
設置場所の環境(温度・湿度・紫外線など)
-
カメラの重量と荷重のかかり方
-
施工時の処理状況(脱脂・圧着・時間経過)
まず、製品そのものの仕様として「屋外用」「高耐候性」と表示されている両面テープであれば、1~3年程度の耐久性が期待できます。
中でも、粘着剤にアクリル系を使用した製品は、耐熱・耐水・耐紫外線性能に優れ、長期使用に向いています。
たとえば、3Mやニトムズといった大手メーカーの屋外用両面テープでは、適切な施工を行えば2年以上耐えることも珍しくありません。
ただし、屋外に設置される場合、以下のような環境要因に注意が必要です。
-
夏の直射日光による高温(壁面温度60℃以上になることも)
-
冬季の氷点下での粘着力低下
-
雨や湿気による粘着面の劣化
-
強風による振動や揺れ
特に温度差が大きい場所では、粘着材が伸縮を繰り返して劣化が進むため、耐久性が短くなる傾向があります。
また、カメラの重量が重いほど、粘着面にかかる力が増し、剥がれやすくなります。500gを超えるカメラでは、両面テープ単独での固定はやや不安定になるため、落下防止の補助策を併用すると安心です。
施工の際には、テープを貼る前に壁面のホコリや油分をしっかり除去し、圧着後はすぐに荷重をかけずに数時間放置することが粘着力の定着に効果的です。これを怠ると、本来の耐久性能が発揮されません。
このように考えると、適切なテープと正しい施工を行った場合、屋外でも1~3年の耐久性は見込めます。
ただし、年に1回程度はテープの状態を確認し、必要に応じて再固定や交換を行うことで、安全性を保つことができます。
両面テープと他の粘着素材の比較
防犯カメラを壁に固定する方法として、両面テープのほかにもさまざまな粘着素材があります。
施工のしやすさや耐久性、再利用性などは素材によって大きく異なるため、それぞれの特徴を比較して選ぶことが重要です。
ここでは、代表的な4種類の粘着素材について、以下のように比較してみます。
| 粘着素材の種類 | 主な特徴 | 向いている条件 | 耐久性 | 再利用性 |
|---|---|---|---|---|
| 両面テープ(屋外用) | 高粘着・簡単施工 | 軽量カメラ、穴開けNG | 中〜高(1〜3年) | 低 |
| 粘着ゲルパッド | 剥がしやすい・再利用可 | 室内向け、賃貸 | 低〜中(数ヶ月〜1年) | 高 |
| ブチルテープ | 防水・密着性◎ | 凹凸面・屋外 | 高(2〜5年) | 低(取り外し困難) |
| シリコン接着剤系パッド | 柔軟で安定性あり | 曲面・細い柱 | 中〜高 | 中 |
それぞれの粘着素材には、長所と短所があります。
両面テープ(屋外用)は最も一般的な選択肢です。強度と手軽さのバランスがよく、DIYでも扱いやすい素材ですが、貼り直しが難しいため位置調整が難しい点に注意が必要です。
再剥離タイプでない限り、剥がす際に壁面に糊残りが生じることもあります。
粘着ゲルパッドは、室内用カメラによく使われており、貼ってはがせるタイプが多く、原状回復がしやすいのが魅力です。ただし、屋外での使用には耐水性や耐熱性が不十分なことが多く、長期設置には向きません。
ブチルテープは、車両や建築現場などでも使われる密着力の高い素材です。凹凸のある外壁にも追従し、耐水性に優れることから、雨の多い地域や海沿いの設置にも向いています。
ただし、粘着力が強すぎるため、撤去時には壁面が傷つくことがあり、取り外しは慎重に行う必要があります。
シリコン接着剤系パッドは、柔軟性に富んでおり、わずかに曲がった面や柱への巻き付け型固定に適しています。ただし、完全硬化までに時間がかかるタイプもあり、施工後すぐに荷重をかけると安定しません。
このように、両面テープは万能ではあるものの、用途や設置環境によっては他の粘着素材の方が適している場合もあります。
例えば、「屋外で強風が吹く地域」であればブチル系、「室内で原状回復を重視」するならゲル系を選ぶのが理にかなっています。
防犯カメラの設置は「固定力」「施工のしやすさ」「環境への適応性」の3つを軸に素材を選ぶことで、より安全かつ長持ちする取り付けが実現できます。
防犯カメラの落下を防ぐための工夫

くらしのヒント箱
防犯カメラを外壁に設置する際、落下を防ぐための対策は非常に重要です。カメラの落下は、機器の破損だけでなく、通行人や車両への事故につながるリスクもあるため、慎重に設置を行う必要があります。
ここでは、実際の施工時に取り入れやすい工夫や補助対策について具体的に紹介します。
まず基本となるのは、「固定方法の強度と安定性の確保」です。
ビス止めであれば下地(柱や間柱)にしっかりと打ち込むこと、両面テープであれば壁面との密着性を高める準備が欠かせません。テープの場合、以下のような下処理が落下防止のポイントになります。
-
壁面の油分・ホコリを中性洗剤やアルコールで除去する
-
粘着面と壁の素材の相性を確認する(凹凸面には粗面対応のテープを使用)
-
テープ貼付後はすぐに荷重をかけず、数時間は静置する
加えて、「補助固定」を施すことも効果的です。
両面テープやマグネットだけで支えるのではなく、結束バンドや金属バンドなどを使って、雨樋・手すり・ポールなどに部分的に固定することで、粘着力が低下した場合にもカメラが完全に落ちることを防げます。以下のような工夫が有効です。
-
カメラ下部に結束バンドを追加し、振動を抑える
-
ブラケットに落下防止用ワイヤーをつける(S字フックで引っかけておく)
-
テープ貼り付け面をL字金具で補強する
また、風の影響を受けやすい場所では「設置角度」や「カメラの形状」も見直してみましょう。
大きな面積で風を受けやすいドーム型より、コンパクトなバレット型のほうが揺れにくいこともあります。風向きを意識して、なるべく壁面と平行に取り付けると風圧を減らすことができます。
さらに、雨や結露による粘着面の劣化も想定しておきましょう。軒下など直接雨のかからない位置を選ぶ、または防水カバーを併用することで、テープやビスまわりの劣化を軽減できます。
施工後も定期的に固定部分を目視確認し、ゆるみや剥がれの兆候があれば早めに対応することが大切です。
このように、外壁に防犯カメラを設置する際は、「一つの固定手段に頼らない」「環境に合った工夫をする」ことを意識すれば、落下トラブルを未然に防ぐことができます。
安全な設置は、防犯性能だけでなく日々の安心感にもつながる重要な要素です。
両面テープで固定後のメンテナンス方法
防犯カメラを両面テープで外壁に固定した後も、そのまま放置してしまうのは避けたほうが良いでしょう。
両面テープは強力とはいえ、経年劣化や環境の影響を受けやすいため、定期的なメンテナンスを行うことで、安全かつ長期間の使用が可能になります。
ここでは、両面テープで固定したカメラのメンテナンス方法を段階的に解説します。
まず最初に確認したいのが「テープの粘着状態」です。外見ではわかりにくい場合もあるため、以下のようなポイントを手で軽く押すなどしてチェックしてみてください。
-
カメラ本体がグラついていないか
-
接着面と壁との隙間ができていないか
-
テープの縁にめくれや浮きがないか
-
テープの一部が変色・劣化していないか(白化や黄ばみ)
異常が見られた場合は、早めに補修または再施工を行うことが重要です。テープを再度貼り直す場合は、古い粘着材をすべて除去し、新しい両面テープを使って再固定しましょう。その際、脱脂と乾燥の手順を丁寧に行うことで粘着力を維持できます。
次に大切なのが「定期清掃」です。カメラ本体やその周辺には、ホコリ、花粉、虫の死骸などが付着しやすく、レンズの汚れが映像品質に影響を与えます。以下の方法で月1回程度の清掃を行うと安心です。
-
柔らかい布やレンズ専用クリーナーでレンズ部分を拭く
-
ブラケット部分にクモの巣やゴミがたまっていないか確認
-
両面テープ周辺に水気やカビが発生していないかチェック
また、固定に使った両面テープの耐用年数に合わせて「交換サイクル」を設けることも有効です。
多くの屋外用両面テープは1〜3年が目安とされており、耐久性を過信せず、定期的に張り替えることで安心して使い続けることができます。
加えて、「環境変化への対応」も見逃せないポイントです。設置時とは異なる状況が発生していることもあるため、例えば以下のような変化がないか定期的に確認しましょう。
-
壁面に直射日光が当たるようになった
-
雨の吹き込みや風向きが変わった
-
近くに植栽が伸びてカメラに干渉している
必要に応じて設置場所の微調整や保護カバーの追加を検討すると、より安定した運用につながります。
このように、両面テープで防犯カメラを固定した後も、定期的な点検と簡単なメンテナンスを行うことで、トラブルを未然に防ぐことができます。
粘着力のチェックとレンズの清掃を習慣にするだけでも、設置後の安心感が大きく変わってきます。
外壁に防犯カメラを両面テープで設置する際の注意点と対策:まとめ
- 両面テープの接着力不足が落下の主な原因となる
- 屋外の温度変化や紫外線が粘着力を劣化させる
- 凸凹のある外壁には密着しづらく落下リスクが高まる
- 防犯カメラの重量と両面テープの耐荷重のバランスが重要
- テープ貼付前に脱脂と乾燥処理を行うことが必須
- 両面テープは「屋外対応」「粗面対応」「高耐候性」を選ぶ
- ゴリラテープは軽量カメラかつ平滑面での設置に有効
- 両面テープ単独で不安な場合は結束バンドなどを併用する
- カメラの設置後はすぐに荷重をかけず静置する
- 外壁に穴を開ける方法は強度に優れるが防水や保証に注意が必要
- クランプやマグネットなど非破壊型の固定手段も選択肢となる
- 屋外で使う場合は落下防止の補助策を必ず検討する
- 両面テープの耐久性は施工と環境次第で1〜3年程度が目安
- 定期的にテープの状態を点検し、劣化があれば貼り替える
- 粘着素材は用途に応じてブチルテープやゲルパッドも選択肢となる
関連記事
防犯カメラをベランダの手すりに取り付け!失敗しない固定方法と設置ルール
防犯カメラを屋外に取り付ける際の業者選びと損しないための費用相場情報を解説
ガレージの防犯カメラ設置場所で効果的なのはどこ?取り付け方法も完全解説
エアコン取り付け業者がひどい?クレームやトラブル事例と失敗を避ける予備知識
食洗機の分岐水栓取り付け業者でおすすめは?費用と対応範囲を比較【保存版】

