
くらしのヒント箱
防犯カメラを屋外に取り付けるときの業者選びについて調べている方の多くは、どこに頼むのが安心で確実なのか、そして費用はどれくらいかかるのかに悩んでいるはずです。
特に一軒家での設置を検討している場合、屋外設置ならではの配線や防水といった課題もあり、専門的な知識が求められることもあります。
この記事では、防犯カメラの設置業者ランキングやおすすめ業者の選び方を紹介しつつ、費用相場や補助金の活用方法についても詳しく解説します。
防犯カメラの屋外取り付けを確実に行いたい方に向け、失敗しない依頼方法や検討すべきポイントを網羅した内容となっています。設置を業者に依頼するか、DIYで自分でやるか迷っている方も、この記事を読むことで最適な判断ができるようになります。
この記事で分かること
- 防犯カメラを屋外に取り付ける際の依頼先の種類と選び方
- 設置業者ごとの特徴や費用相場の違い
- 一軒家への設置にかかる具体的な工事内容と注意点
- 防犯カメラ設置に使える補助金制度の活用方法
本ページはプロモーションが含まれています
防犯カメラを屋外に取り付ける際の業者の選び方

くらしのヒント箱
- 防犯カメラ設置はどこに頼むのが正解?
- 防犯カメラ設置業者ランキング おすすめ情報
- 一軒家の防犯カメラ取り付け工事費用
- 設置のみを依頼する場合の注意点
- ホームセンターで防犯カメラ取り付けは可能?
- ヤマダ電機の防犯カメラ設置工事の内容
- ケーズデンキの防犯カメラ設置費用の目安
- 防犯カメラ設置補助金の活用方法
防犯カメラ設置はどこに頼むのが正解?
防犯カメラの設置を検討する際、最初に悩むのが「どこに頼むべきか」という点です。選択肢は複数あり、電気工事店、防犯カメラ専門業者、家電量販店、ホームセンター、さらにはDIYまでさまざまです。
それぞれにメリットと注意点がありますので、自分の状況に合った方法を選ぶことが重要です。
例えば、コストを抑えたい方や配線工事が不要な無線カメラを選んだ方は、自分で設置(DIY)するという選択肢があります。
近年では、初心者でも設置しやすいWi-Fi対応のカメラが販売されており、簡単なマニュアルも付属している製品が増えています。
ただし、設置場所や配線の取り回し、防水処理に不安がある場合は、仕上がりや安全面に課題が残ることも考えられます。
一方で、確実性やセキュリティを重視する場合は、専門業者に依頼する方が安心です。電気工事士の資格が必要な場合や、防水・防塵対策をしっかり行いたい場合は、専門の技術を持つプロの力が必要になります。
特に屋外に設置する場合、配線が雨風にさらされるため、防水性能や固定の強度が求められます。
このように、選ぶべき依頼先は設置目的や環境、予算によって変わります。以下に代表的な依頼先の特徴をまとめました。
| 依頼先の種類 | 特徴と適したケース |
|---|---|
| 電気工事店 | 費用を抑えたい場合に適しているが、商品選びは自分で行うことが多い |
| 防犯カメラ専門業者 | 商品選びから設置まで一貫して対応。性能重視や商業施設向けに適している |
| 家電量販店(例:ヤマダ電機) | 一般家庭向けのセット販売が充実。設置サービスも比較的手軽に依頼できる |
| ホームセンター | カメラ販売のみのケースが多く、設置は別途業者を探す必要がある |
| DIY(自分で設置) | 費用を抑えられるが、技術と知識が必要。屋外設置には不向きな場合も |
最適な依頼先を選ぶためには、事前に「何をどこまで業者に頼むか」「どんな性能のカメラが必要か」「どこに設置するか」を整理しておくとスムーズです。
防犯カメラ設置業者ランキング おすすめ情報

くらしのヒント箱
防犯カメラの設置を業者に依頼する場合、どの業者が信頼できるのかを判断することは非常に大切です。ランキングや評価を参考にすることで、施工の質や価格帯、アフターサービスの傾向を把握しやすくなります。ここでは、くらしのマーケットなどで高評価を得ている業者の傾向や、おすすめポイントについて解説します。
実際のランキングでは、以下のような基準で業者が選ばれています。
-
顧客評価(★の平均点やレビュー件数)
-
価格の明確さと納得感
-
対応スピードや丁寧なコミュニケーション
-
工事の仕上がりとアフターフォローの充実度
例えば、ある東京都内の業者は「施工実績が非常に多く、価格は25,000円から」と比較的リーズナブルな価格設定にもかかわらず、4.9以上の高評価を維持しています。丁寧なヒアリングや、設置場所の適切なアドバイスが評価されているポイントです。
おすすめされる業者の特徴としては、以下のような点が挙げられます。
-
下見なしでも明確な見積もりが提示される
-
工事費込みのパッケージプランがある
-
高所や特殊な設置環境にも対応している
-
地元密着型で迅速な対応が可能
ランキング上位の業者ほど、施工の質と価格のバランスが良く、初めて設置する人でも安心して任せられる傾向があります。ただし、人気業者ほど予約が取りづらい場合もあるため、余裕を持ったスケジュールで依頼するようにしましょう。
一軒家の防犯カメラ取り付け工事費用

くらしのヒント箱
一軒家に防犯カメラを設置する場合、工事費用はカメラの台数や設置場所、使用する機材の種類によって大きく異なります。
最も基本的な構成であっても、配線や電源確保の必要があるため、ある程度の工事費用を見積もっておく必要があります。
目安として、電気工事店に依頼した場合の設置費用は1台あたり4万円〜10万円、防犯カメラ専門店であれば10万円〜15万円程度が相場です。
さらに、警備会社に依頼すると、セキュリティシステムとの連携費用や月額利用料も発生し、初期費用は1台あたり25万円〜50万円になるケースもあります。
一軒家の場合、設置箇所として以下のような場所が一般的です。
-
玄関・門まわり
-
駐車場・カーポート
-
裏口・勝手口
-
庭や敷地の周囲
これらをすべてカバーしようとすると、複数台のカメラが必要になるため、設置費用はさらに増える可能性があります。
費用を抑えるためには、以下のような工夫が効果的です。
-
ワイヤレスカメラの導入(配線工事が不要)
-
自分で取り付けられる機種を選ぶ(DIY)
-
防犯カメラ設置補助金を活用する
-
複数の業者に相見積もりを取る
特に補助金については、自治体によって内容が異なるため、地元の市区町村のウェブサイトなどで最新情報を確認することが大切です。
最終的には、設置するカメラの性能や台数、配線の難易度などを総合的に判断しながら、信頼できる業者を選びましょう。安さだけで選ぶのではなく、必要な性能とサービス内容を満たしているかを確認することが、納得のいく設置につながります。
設置のみを依頼する場合の注意点

くらしのヒント箱
防犯カメラの設置だけを業者に依頼する場合、機材の購入や選定を自分で行うことが必要になります。
設置作業に関しては専門家に頼めますが、機器や配線の仕様を理解しておくことが重要です。
たとえば、屋外設置の場合はIP66以上の防水・防塵性能を持つカメラが推奨されます。そこまで考慮しないと、設置後に雨水や埃で故障する可能性があります。
また、配線や電源に関する工程についても整理しておきましょう。USB電源・延長コード対応など幅広いタイプがありますが、必要なケーブル長や給電方式が合っていないと、最終的に正常に動作しないトラブルが起こり得ます。
ジョイントボックスやPF管、防水テープといった部材も、自分で用意することになります。これらを抜けなく準備できるかどうかが、作業後の仕上がりや安全性に直結します。
さらに、施工範囲の確認も必須です。業者に「取り付けのみ」を依頼している場合、配線の引き込み、設定、テストまで含まれているのか明確に確認してください。
業務が分担されていると、想定外の作業が自己負担になりかねません。見積もりの段階で作業範囲を明確化しておくことが、後々のトラブル防止になります。
ホームセンターで防犯カメラ取り付けは可能?

くらしのヒント箱
ホームセンターでも防犯カメラを販売しているケースは増えています。たとえば、商品コーナーに並ぶWi‑Fi対応カメラや防水仕様の屋外用モデルなどを購入できます。
ただし、取り付けをその場で依頼できる場合は限られており、基本的には「設置は別途業者に依頼する必要がある」と考えておいたほうが無難です。
ホームセンターで提供されている補助部材(PF管や接続ナット、防水パテなど)を一括で購入できる点は利点です。
しかし、設置作業をそのまま任せることは難しいため、DIYで設置するか、別途専門業者を探すという流れになります。
さらに、設置サービスがある店舗でも、技術の質や保証範囲にばらつきがあるため、信用できる業者との比較検討が必要です。
したがって、ホームセンターはカメラ本体や補助部材の購入には便利ですが、施工品質や後のケアを重視する場合には、専門業者への依頼が安心です。
ヤマダ電機の防犯カメラ設置工事の内容
ヤマダ電機では、防犯カメラの販売だけでなく、設置工事サービスも提供しています。屋外設置を希望する場合でも、機種選びから施工まで一貫したサポートが受けられるのが特長です。
カメラ購入時には、店頭または訪問見積りにて設置環境の相談が可能で、電気工事士の有資格者が施工にあたります。
サービスの主な内容は次のとおりです:
| 作業項目 | 内容の一例 |
|---|---|
| 設置場所の確認 | 配線ルートや電源位置を現地で確認し、適切な設置位置を提案 |
| 配線工事 | 屋外ではPF管などを用いた防水対策も含めた配線処理を実施 |
| カメラの固定・画角調整 | カメラの向きや高さを調整し、映像範囲を最適化 |
| 映像機器との接続 | 録画装置やスマホアプリとの接続・設定サポート |
| 動作テスト | 通電・録画・映像確認まで一通りのチェックを実施 |
| アフターサービス | 初期不良の対応、使い方のサポート等を店舗またはメーカーが対応 |
なお、設置費用は設置台数や配線距離、壁面の材質、高所作業の有無などによって変動します。目安として、1台あたりの設置工事費用は約11,000円(税込)以上が一般的ですが、特殊な施工が必要な場合には別途追加費用が発生することもあります。
また、ヤマダ電機では見積り(約3,300円/税込)を実施しており、見積後にキャンセルとなった場合でもこの費用は返金されません。そのため、事前に施工内容と費用の内訳をよく確認し、不明点があれば必ず質問するようにしましょう。
サービス内容や対応範囲は、店舗ごとに若干異なるケースもあります。地方店舗などでは対応業者が異なることもあるため、具体的な施工希望がある場合には、事前の相談が非常に重要です。
ヤマダ電機のような大手量販店を利用することで、保証体制やアフターサポートの安心感を得られるという点も、依頼先選びのポイントとなるでしょう。
ケーズデンキの防犯カメラ設置費用の目安

くらしのヒント箱
ケーズデンキでは、防犯カメラ本体や周辺機器の販売は行っていますが、設置工事には対応していません。
テレビやエアコンなどの家電については配送・設置サービスを提供していますが、防犯カメラに関しては対象外となっており、購入後の取り付け作業は購入者自身で行う必要があります。
ケーズデンキでできること
-
店頭およびオンラインショップでの防犯カメラの購入
-
カメラ選定時の簡易的な商品説明
-
他の家電と同時購入によるセット割引などの販売キャンペーン(不定期)
ケーズデンキでは対応していないこと
-
防犯カメラの設置・取り付け工事
-
配線処理や電源工事
-
高所作業や屋外設置などの施工全般
-
見積もりや下見の訪問対応
このように、防犯カメラの購入はケーズデンキで可能ですが、設置までを依頼したい場合は、別途専門の工事業者を手配する必要があります。
設置を希望する場合の対応策
防犯カメラの取り付けまでをスムーズに進めたい場合、以下のような対応が考えられます。
-
クラウド型やDIY対応カメラの購入
工事不要で設置できるワイヤレスタイプや置き型のカメラであれば、DIYでも比較的簡単に取り付けが可能です。 -
専門業者への設置依頼
くらしのマーケット、ミツモアなどのサービスを活用すると、地域の施工業者を探して見積もりを比較できます。 -
電気工事士に直接依頼
屋外配線や電源工事が必要な場合には、電気工事士の資格を持つプロに任せると安心です。
ケーズデンキでは、防犯カメラの設置サービス自体は提供していません。そのため、設置を前提に購入を検討している場合は、最初から「設置も依頼できる業者」または「DIYで設置可能な製品」を選ぶことが重要です。
販売店であるケーズデンキで購入したカメラを、外部業者に依頼して取り付けてもらうという形が現実的な選択肢となります。
購入の際は、製品の性能だけでなく、「誰がどのように設置するのか」までを見据えて検討すると、トラブルや追加費用の発生を防げます。ケーズデンキでの購入を検討する場合は、必ず設置面の手配を自身で行う必要がある点を理解しておきましょう。
防犯カメラ設置補助金の活用方法

くらしのヒント箱
自治体によっては、防犯目的で屋外カメラを設置する場合に補助金制度を提供していることがあります。
ただし、補助対象や支給額、申請手順は地域によって異なるため、必ず最寄りの市区町村の窓口や公式サイトで最新情報を確認する必要があります。
申請の際に共通して注意すべきポイントを以下に整理しました。
-
補助対象となる地域や設置条件(住宅の種類や用途、設置箇所など)
-
補助金の支給上限額と対象となる費用(本体費用/工事費など)
-
申請に必要な書類(領収書、設置業者の見積書、防犯計画など)
-
補助金申請のタイミング(事前申請が必要か、工事後でもよいか)
-
支給決定までの期間(自治体により数週間~数ヶ月)
補助金を活用することで、自己負担を数万円から十数万円軽減できるケースもあります。とはいえ、補助制度を利用するためには、一定の条件を満たし、正しく申請手続きを進めることが求められます。
申請前には、住宅の構造や設置台数、機種の性能などが補助対象かどうかをよく確認し、その内容に応じた証明書類を整えておくことが重要です。
申請が認められた後は、支給額が予想より少なくなるケースもあるため、多めに見積もっておくと安心です。
この制度を利用すれば、防犯目的でカメラ設置を考えている方にとって、経済的な負担を減らす有効な手段となります。申し込み条件や締め切りなど、早めに手続きを始めるのが得策です。
防犯カメラを屋外に取り付ける場合の業者とDIYを比較

くらしのヒント箱
- 屋外取り付けをDIYするメリット
- 設置を自分でする手順と注意点
- 配線や電源工事の難易度と資格の必要性
- 屋外設置に必要な防水・防塵性能とは
- 設置場所の選び方と画角調整のポイント
- DIY向けおすすめ防犯カメラ製品の特徴
- 費用面で見る業者依頼とDIYの違い
屋外取り付けをDIYするメリット

くらしのヒント箱
防犯カメラの屋外設置をDIYで行うことには、いくつかの明確なメリットがあります。最大の利点は、工事費用を大幅に削減できる点です。
専門業者に依頼する場合、1台あたり数万円の工賃が発生することが一般的ですが、自分で設置すれば機材費のみで済みます。
特に、ワイヤレス型の防犯カメラであれば、配線作業もほとんど不要で、初心者でも比較的簡単に取り付けられます。
また、設置場所を自由に選べるという点も大きな魅力です。業者依頼では時間や作業範囲の制約がありますが、DIYなら納得のいくまで位置を試行錯誤できます。
たとえば、玄関だけでなく裏口や物置の死角などにも気軽に取り付けが可能です。さらに、最近のクラウド型カメラはスマートフォンからの映像確認もできるため、接続設定もシンプルになってきています。
もちろん、DIYにはデメリットもあります。たとえば、防水処理や固定の強度が不十分な場合、カメラが故障したり落下するリスクがあります。
また、電源の確保が難しい場所への設置や、高所での作業には危険が伴います。そうしたリスクを考慮し、安全な設置環境が整っている場合にDIYを選ぶのが望ましいです。
このように、DIYでの屋外カメラ設置はコストを抑えつつ、自由度の高い防犯対策を行いたい方にとって有効な選択肢です。
ただし、安全性と機能性をしっかり確保できるよう、製品選びや設置作業には十分な注意が求められます。
設置を自分でする手順と注意点

くらしのヒント箱
防犯カメラを自分で設置する場合、基本的な手順を正しく理解しておくことが大切です。手順を誤ると、設置後に映像が映らなかったり、雨風で機器が故障するなどのトラブルにつながる恐れがあります。
一般的な設置手順は以下のとおりです。
-
設置場所の選定
-
配線ルートの確認と処理
-
カメラの固定
-
録画装置やスマホとの接続
-
映像確認とテスト
最初のステップでは、死角をできるだけなくすように、玄関や駐車場、裏口などをバランスよくカバーする配置を検討します。
また、設置面の材質(コンクリート、木材など)や配線の取り回しを確認し、対応する工具や部材を事前に揃える必要があります。
次に、配線が必要なカメラであれば、電源や録画装置へのケーブル接続が必要になります。特に屋外の場合は、PF管でコードを保護し、接続部は自己融着テープや防水パテでしっかりと処理しておきましょう。
モールやジョイントボックスを使うことで、配線の露出を最小限に抑え、安全性も確保できます。
固定時には、強風や雨でも外れないよう、壁材に適したビスやアンカーを使用し、ドライバーまたは振動ドリルで確実に取り付けることが重要です。
また、取り付け後は必ず角度を調整し、録画範囲に死角がないかを映像で確認します。
注意点としては、誤ってケーブルを破損させたり、屋外設置時に防水対策を怠ったりしないことが挙げられます。また、高所作業は転落事故のリスクもあるため、無理な作業は避けるようにしましょう。
DIYでの設置は自由度が高い反面、すべてを自分で管理する責任も伴います。このため、設置に不安がある場合は、カメラのみを購入し、取り付けは業者に依頼する選択肢も検討してみてください。
配線や電源工事の難易度と資格の必要性
防犯カメラの設置において、配線や電源の工事は難易度が高くなりやすいポイントです。
特に屋外設置の場合は、電源の確保、長距離のケーブル敷設、防水処理などが求められ、初心者にとっては障壁になりがちです。
まず、電源についてですが、コンセントが近くにない場合は延長コードを使用するか、電源の増設が必要になります。
延長コードは簡易な方法ですが、防水性のある屋外対応の製品を選ばなければ故障や感電のリスクがあります。
また、配線をむき出しにしたままでは、雨風や日光で劣化しやすく、つまずき事故の原因にもなります。このような危険を防ぐためには、PF管やモールで配線を保護し、接続部は防水パテやテープで処理することが基本です。
配線工事の難しさは、次の要素によって変わります。
-
配線距離の長さ(長距離ほど電圧降下や信号劣化の懸念)
-
通線経路の複雑さ(壁や天井を通す場合、工事経験が必要)
-
屋外環境(雨、風、日差し、虫などからの保護対策)
このように、配線や電源工事は機器の動作に直結する重要な工程であるため、知識と経験が必要です。
DIYに挑戦する場合でも、最低限の電気工事知識と、安全対策を身につけたうえで作業を行いましょう。自信がない場合は、無理をせず専門業者に依頼する方が確実です。
最終的に、安全で長持ちする防犯システムを実現するためには、適切な設置と配線処理が欠かせません。技術的な自信がある場合を除き、難易度の高い工事部分はプロの手を借りる選択肢も検討しましょう。
屋外設置に必要な防水・防塵性能とは

くらしのヒント箱
屋外に防犯カメラを設置する際は、カメラ本体が雨や風、ほこりなどの外的要因に耐えられるかどうかが非常に重要です。
この性能を判断する際に参考にされるのが「IP規格」と呼ばれる国際的な保護等級です。製品の仕様書やパッケージに「IP66」「IP65」といった表記を見かけたことがある方も多いのではないでしょうか。
この「IP」の後ろにある2つの数字は、それぞれ防塵性能と防水性能の高さを表しています。前の数字が防塵、後ろの数字が防水を示し、数値が大きいほど保護性能が高いとされています。
たとえば、「IP66」の場合、完全な防塵構造で、かつ強い噴流水にも耐えられる設計です。屋外用としては、この「IP66」以上を基準に選ぶと安心です。
下記に、一般的なIP規格の目安を示します。
| IP等級 | 防塵レベル(1~6) | 防水レベル(1~8) | 使用の目安 |
|---|---|---|---|
| IP65 | 完全防塵/噴流水に耐える | ○ | 屋外の軒下などで使用可能 |
| IP66 | 完全防塵/強い噴流水に耐える | ◎ | 雨風の直接当たる屋外に適している |
| IP67 | 完全防塵/一時的な水没にも耐える | ◎ | 雨量の多い地域や風雨が強い場所向き |
| IP68 | 完全防塵/長時間の水没に耐える | ◎ | 特殊環境(例えば浸水しやすい場所)用 |
一方で、IP44やIP55程度の性能では、台風や吹き込み雨には対応できない可能性があります。そのため、屋外用に購入する際は、IP66以上の製品かどうかをまず確認しましょう。
また、防塵防水性能は経年劣化する可能性もあります。長く使用するためには、設置時の防水処理(たとえば配線接続部への防水パテや自己融着テープの使用)も忘れてはいけません。IP等級の高い製品であっても、施工方法が甘ければ防水性は確保できません。
このように、防水・防塵性能は製品選びの基準であると同時に、設置工事の品質とも深く関わっています。見た目や価格だけで選ばず、設置環境に合った保護性能をもつカメラを選びましょう。
設置場所の選び方と画角調整のポイント
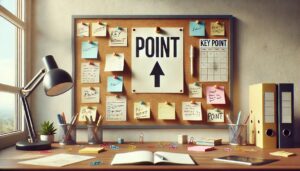
くらしのヒント箱
防犯カメラを効果的に活用するには、「どこに」「どの向きで」設置するかが非常に重要です。
高性能なカメラを使っていても、設置位置や画角が適切でなければ、死角ができてしまい、本来の目的を果たせない可能性があります。
設置場所を選ぶ際には、まず「何を監視したいのか」を明確にする必要があります。住宅であれば、代表的な設置ポイントは以下の通りです。
-
玄関(人の出入りの記録)
-
駐車場(車上荒らし・盗難対策)
-
裏口や勝手口(死角になりやすい)
-
敷地の外周(不審者の侵入経路)
このとき、できるだけ高い位置にカメラを設置することで、広い範囲をカバーできるうえに、いたずらや破壊行為からの防御にもつながります。
ただし、高すぎると映像が見づらくなるため、地上から2.5~3メートル程度が一般的な設置高さです。
画角調整においても、注意すべきポイントがあります。カメラの多くは「水平画角」「垂直画角」が設定されており、例えば水平120度のモデルであれば、1台でも広範囲をカバーできます。
とはいえ、広角すぎると映像が歪みやすく、人物やナンバープレートが確認しづらくなるケースもあります。
このため、以下のようなバランスを考慮することが大切です。
-
広角カメラ:死角を減らせるが、詳細確認は苦手
-
中望遠タイプ:顔や車両番号の識別に適しているが、範囲は狭くなる
また、太陽光の反射や逆光によって映像が見づらくなることもあります。直射日光の影響を受けにくい方角や、レンズに庇(ひさし)をつけるといった対策が有効です。夜間撮影が目的であれば、赤外線センサー付きやナイトビジョン機能の有無も確認しましょう。
こうして考えると、設置場所と角度はカメラの性能を最大限に活かすためのカギとなります。
可能であれば、事前にスマホなどで視野確認をしながら、位置と角度を微調整してから固定するのが理想的です。設置後に映像をチェックし、死角が残っていないかも確認しておきましょう。
DIY向けおすすめ防犯カメラ製品の特徴
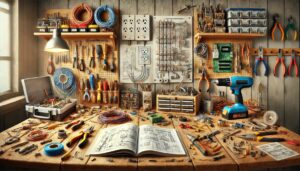
くらしのヒント箱
DIYで防犯カメラを設置する場合、製品選びが非常に重要です。初心者にとっては、設置が簡単で操作性が高い製品であることが大きなメリットとなります。
そのため、配線工事が不要なワイヤレスタイプや、電源と録画機能が一体型になったモデルが人気です。
たとえば「Safie One」のようなクラウド型カメラは、次のような特徴を備えています。
-
無線LAN接続対応:配線不要で設置が簡単
-
クラウド録画:SDカード不要で録画内容をスマホやPCで確認可能
-
コンパクトサイズ:室内外問わず目立たず設置できる
-
人感検知・通知機能:異常があればスマホに通知
-
ナイトビジョン対応:夜間でもしっかり映像を記録
このようなカメラであれば、工事の手間がほとんどかからず、置くだけですぐに使えるものもあります。また、アプリでの操作が直感的にできるものが多く、初めて防犯カメラを扱う方でも安心です。
DIY向け製品を選ぶ際には、以下のようなポイントを基準にすると選びやすくなります。
| チェックポイント | 内容例 |
|---|---|
| 電源方式 | バッテリー式、USB式、ACアダプタ式など |
| 通信方法 | Wi-Fi、LTE対応、Bluetoothなど |
| 記録方法 | クラウド録画、SDカード、NAS連携など |
| 設置形態 | 置き型、マグネット、ネジ固定など |
| 対応機能 | 防水・防塵、暗所撮影、動体検知など |
このように、自分で設置しやすいかどうかを前提に選ぶと、DIYでの取り付けがスムーズに進みます。ただし、屋外に設置する場合は防水・防塵性能(IP66以上)が必要になるため、対応製品を選ぶよう注意が必要です。
防犯対策の第一歩として、手軽に導入できるDIY向けカメラは非常に有用です。長期的な運用も考慮して、アフターサポートがしっかりしているメーカー製品を選ぶことをおすすめします。
費用面で見る業者依頼とDIYの違い

くらしのヒント箱
防犯カメラの導入にあたって、「業者に依頼するか」「DIYで設置するか」で悩む方も多いのではないでしょうか。それぞれの方法にはメリットとデメリットがあり、特に費用面では大きな差が出ます。
まず、DIYで設置する場合の費用は、基本的にカメラ本体代のみで済みます。ワイヤレスカメラであれば1台あたり1万円〜5万円程度で購入でき、録画機能やアプリ連携が含まれている製品もあります。また、工事費がかからない分、初期費用を大きく抑えられるのが最大の魅力です。
一方、業者に設置を依頼する場合は、以下のような費用がかかります。
| 項目 | 費用目安(1台あたり) |
|---|---|
| カメラ本体代 | 3万~8万円程度 |
| 設置工事費 | 1万~5万円程度(工事内容により変動) |
| 配線工事・高所作業など | 別途1万~3万円以上かかる場合あり |
| 合計 | 5万~15万円以上が一般的 |
特に屋外での高所設置や、建物内部への配線引き込み作業が必要な場合は、工事費が高額になる傾向があります。また、録画機器やモニターも必要であれば、その分さらにコストがかかります。
このように、初期投資を抑えたい場合や、簡単な設置環境であればDIYの方が圧倒的に安価です。しかし、設置場所が複雑であったり、確実な防犯性能を求める場合は、業者による施工が安心でしょう。
加えて、業者に依頼する場合は、以下のようなメリットもあります。
-
専門知識をもった技術者による設置
-
保証やアフターサポートが充実
-
配線処理や防水施工が丁寧
ただし、DIYにも業者依頼にも「向いている人・向いていない人」がいます。たとえば、電動工具の使用に慣れている方や、配線に理解がある方であればDIYでも問題ない場合があります。逆に、高齢の方や防犯リスクを特に重視する方には、業者依頼のほうが適しています。
費用面だけでなく、設置の難易度や将来的なメンテナンスも考慮し、目的に合った方法を選ぶことが大切です。
防犯カメラを屋外取り付けする業者選びと設置方法の総まとめ
- 屋外設置には防水・防塵性能(IP66以上)のあるカメラを選ぶ必要がある
- 電気工事士の資格が必要な作業は無資格ではできないため業者依頼が安心
- 防犯カメラの設置は家電量販店、専門業者、DIYなど複数の選択肢がある
- 防犯性と施工品質を重視するなら防犯カメラ専門業者の利用が有効
- 一軒家の設置費用は1台あたり4万~15万円が相場
- ホームセンターは本体販売のみで設置は基本的に対応していない
- ヤマダ電機では設置工事サービスも提供されており、見積もりも可能
- ケーズデンキはカメラ販売のみで、設置工事には対応していない
- DIY設置は費用を抑えられるが、防水処理や高所作業のリスクがある
- 設置場所は死角をなくすよう玄関・裏口・駐車場周辺が推奨される
- 水平・垂直画角の調整で録画範囲を最適化することが効果的
- ワイヤレスカメラやクラウド録画型はDIYに向いている
- 配線や電源工事には専門知識と安全対策が不可欠
- 見積もり時に作業範囲や費用の内訳を明確にしておくとトラブル防止になる
- 自治体によっては補助金制度があり、費用負担を軽減できる場合がある
関連記事
外壁に防犯カメラを両面テープで取り付けると落ちる?失敗を防ぐ設置方法と対策
ガレージの防犯カメラ設置場所で効果的なのはどこ?取り付け方法も完全解説
防犯カメラをベランダの手すりに取り付け!失敗しない固定方法と設置ルール

